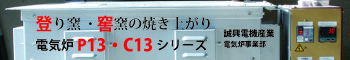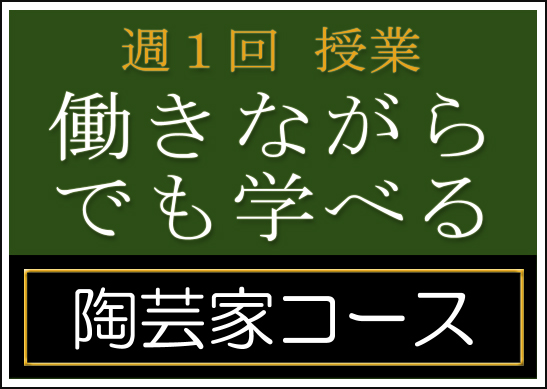原 憲司
桃山黄瀬戸再興
東京生まれ。原材料を徹底的に吟味し、可児市の久々利に築いた半地下式の窖窯で、加藤唐九郎が一時的にしかなしえなかった黄瀬戸「菖蒲手」(あやめで)を再興した。
美濃の名窯・幸兵衛窯で働く
1947年東京の下町に生まれた原憲司氏が、職としてイメージしたのが盆栽師。しかし、夏に訪れた美濃で、陶磁器試験場長の五代加藤幸兵衛に偶然出会い、その日から幸兵衛窯にお世話になるという劇的な展開が待っていた。
幸兵衛窯は、江戸城に染付を納めた美濃の名窯で、原氏は五代の長男・卓男の助手として働くことになった。フィンランドでペルシャ陶器を学び、95年に三彩で人間国宝に認定された卓男の陶壁づくりを手伝うのが当初の仕事で、以来原氏は13年間助手を勤め、82年に久々利で独立した。
久々利には、美濃焼を現代に甦らせた荒川豊三(1894〜1985)の窯がある。荒川は1930年に、国宝の「卯花墻」(うのはながき)とそっくりの陶片を久々利の大萱(おおがや)で発見。それが契機となって古窯群の調査が始まり、「志野、黄瀬戸、織部などは瀬戸でつくられた」という定説がひっくり返されたのである。
荒川は大萱に窯を築いて志野の再現に取り組んだが、当時の美濃は磁器が主流。志野の原材料から焼き方までを一から探り出すのに、5年の歳月が流れた。その業績が評価されて1955年に「志野と瀬戸黒」の人間国宝に認定され、その荒川と同じく桃山陶に魅せられたのが加藤唐九郎(1898〜1985)だ。
窖窯で菖蒲手を再興
唐九郎は、20歳の頃から瀬戸や美濃の古窯調査を行いながらその再現に取り組み、黄瀬戸の「菖蒲手」<ルビあやめで>の再現に初めて成功した。「菖蒲手」は「油揚手」とも言われ、薄づくりの柚肌が特徴で、桃山の一時期につくられたもの。一方、17世紀後期に大量に焼かれた「菊皿手」は光沢のある黄色で、いずれも唐九郎が区分して命名したものだ。
独立した原氏が、久々利に当初築いたのが割竹式登り窯。しかししばらくして、美濃の単室の大窯を念頭においた窖窯に切り換え、黄瀬戸に本格的に取り組む態勢を整えた。
13年間の充電期間を経て原氏が目標にしたのは、桃山期の名品で、呼称の元となった井上家旧蔵の「菖蒲文鉦鉢」のような菖蒲手。唐九郎が復元に一時期だけ成功したが、それ以降は焼くことができなくなっていたのだ。
焼き物づくりの過程で原氏がこだわったのが、原材料の吟味。素材がもっているものが自ずと焼き上がりに出てきて、その力を無視できないからだ。美濃焼のもぐさ土は山中にポケット状に散在し、その性質が微妙に異なる。原氏はいろいろな土を、他の原材料と組み合わせ、何万回も焼成試験を繰り返して現在の素材にたどり着いた。その結果、識者もうならせるほどの優雅な黄瀬戸を再興することができたのだ。
そして近年は、織部や井戸茶碗などに手を伸ばすなど、制作意欲はいささかも衰えていない。
HARA KENJI PROFILE
1947年 東京都江東区に生まれる
1969年 加藤卓男に師事
1982年 岐阜県可児市で独立
1990年 作陶20年 黄瀬戸 原憲司展(松坂屋本店)
2001年 個展(日本橋三越本店)
2001年 岐阜県美術館買上げ収蔵(黄瀬戸茶盌)
2003年 個展(日本橋三越本店、大阪なんば髙島屋)
銀座黒田陶苑などで個展を多数開催