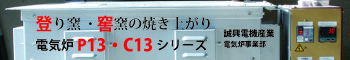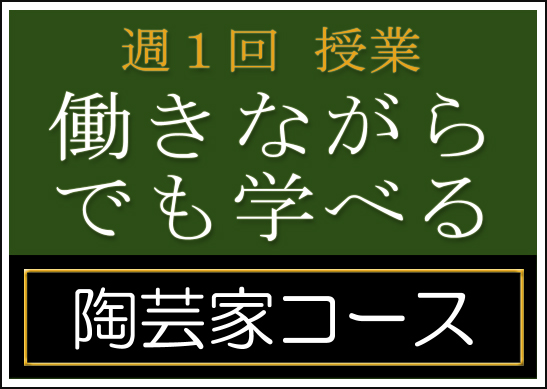志賀暁吉
青瓷を極める
大堀相馬焼の窯元に生まれた志賀暁吉氏は、2007年の日本陶芸展で大賞を受賞。29歳という若さと青瓷による大壺の受賞だったため、二重の衝撃を陶芸界に与えた。
高い相馬焼の製陶技術
福島県の海側で焼かれている相馬焼の拠点は、二カ所に分かれている。一つは相馬市内の中村で、もう一つは東京よりの浪江町。どちらも相馬焼独特の「青罅(あおひび)」と野馬の「駒絵」で知られているが、作風はまったく異なる。前者は御用窯で茶陶を中心に焼いているのに対して、後者は民陶として日用雑器を焼く。かつてはその二カ所の焼き物を相馬焼と総称していたが、距離もあり作風も異なるので、現在は前者を相馬駒焼、後者を大堀相馬焼と呼んで区別している。
300年前に始まるといわれている大堀相馬焼で焼かれていたのは、暮らしに欠かせない茶碗、皿、片口、徳利の雑器に加え、壺や甕などの実用器だ。それに灰釉、糠白釉、飴釉、黒釉、緑釉などを流し掛けしている。象嵌、飛鉋(とびがんな)、型押、貼付などの加飾も多様で、その技術水準は各地で指導するほどの領域に達していた。
特筆すべきは薄手で精巧な轆轤技による山水土瓶で、質、量とも益子や信楽をしのぐほどであった。明治から始まる「青罅」や「駒絵」も、相馬に蓄積されていた技術によって生み出されており、日本陶芸展で受賞した志賀暁吉氏の「青瓷壺」は、大堀相馬焼伝来の高度な轆轤技と、貫入青磁である「青罅」によって支えられていると誰もが思った。
陶芸作家を目指す
1977年に大堀相馬焼の窯元・吉峰窯の長男として浪江町で生を授かった志賀暁吉氏であったが、18歳で専門校の陶芸科に入るまでは土に触れることはほとんどなかった。さらに、大堀で焼かれてきたものに対しては、ほとんど興味を示さなかった。 高校までは野球に熱中していた志賀氏は、大人として職業を決める段階になって初めて、しかも漠然と焼き物を選んだ。そして半年ほどしてから陶芸作家になることを決め、好きだった南宋や北宋の青瓷を極めることを目標にした。そのため、専門校では青瓷のテストピースをつくることに集中し、夏休みなどは青磁作家の鈴木三成氏の工房に通い、卒業してからも教えを受けた。しかし、どうして作品にもキズが入り、土を吟味するのに3年を要した。
吉峰窯の一角に建てた工房は土足厳禁であった。さらに、3坪あまりの轆轤部屋の窓には黒い紙がぴたりと貼られていた。素地にほこりが付き、キズになってしまうという無駄な失敗をしたくないためだ。また、釉薬を掛ける部屋を含めた床は磨かれて光っており、塵一つ見当たらなかった。さらに轆轤を挽くときには、専用のつなぎを必ず着用した。普段着に吸着している塵が飛び散らないようにするためだった。
土の選択や調合に3年間を要した志賀氏の土は、黄土、磁土、半磁土の3種を混ぜたもので、地元の土は今でも一切使わない。轆轤で挽いてからほぼ一晩乾かし、仕上げのけずりはやや硬めのステンレス製のカンナで行う。釉掛けは、エアーコンプレッサー。4〜5回吹き掛けて、厚みを3mmほどにしているが、釉薬は貫入が入るものとそうでないものの2種で、色合いはどちらも青瓷の頂点と評価されている北宋の汝窯<(じょよう)に近い。志賀氏は貫入の入らない青瓷釉を「淡青瓷」としているが、青瓷釉よりやや淡く汝窯により近い色合いになっているのだ。
吉峰窯が浪江町で陶業を始めて100年になるが、2011年の東日本大震災により、使い慣れた窯や道具など一切をそこに置いたまま、離れざるをえなくなってしまった。2年前に3代目の父親を亡くし、いまは青瓷を極める独自の道を歩み続ける決意を強くしている。
SHIGA AKIOSHI PROFILE
1977年 福島県浪江町に生まれる
2000年 文化学院芸術専門学校陶磁科卒業
2000年 鈴木三成氏に指導を受ける
2004〜07年 伝統工芸新作展入選
2004・06年 益子陶芸展入選
2004・07年 日本伝統工芸展入選
2005年 日本陶芸展入選
2007年 日本陶芸展大賞
2010年 日本工芸会正会員