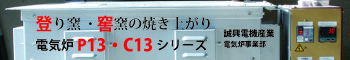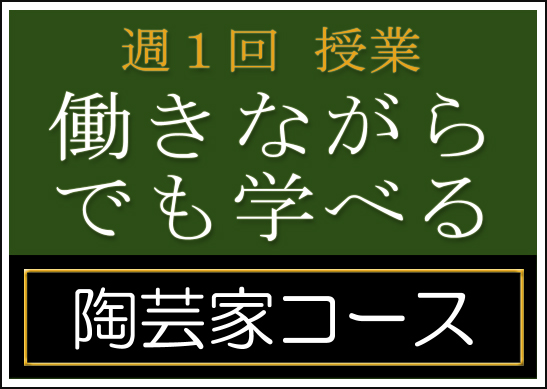篠原 希
焼き破りの新美学
1972年大阪生まれで、当初粉引を目指したが窯変美に魅せられて焼締に傾倒。
焼成中にキズを入れるなどのやり方で、古琵琶湖が精製した陶土の素材感を引き出す。
古琵琶湖層の陶土を
8世紀から始まる信楽焼を支えたのは、地下に眠る豊富な陶土と丘陵地帯をおおう豊かな森林。約400万年前に三重の上野盆地から起こった地殻変動は、信楽を経て滋賀の近江盆地に達した。それにより、南にあった古琵琶湖は徐々に北に移動して現在地に、湖底にあった伊賀を含む信楽一帯は隆起して現在のような地形が形づくられた。
信楽焼と伊賀焼の作風は異なるが、焼き上がりや風合いがなんとなく似ているのは、ともに砂、小石を含んだ古琵琶湖層から陶土を採取してきたからで、その厚さは200から1500m。信楽の標高が約300mだから、両産地はおよそ標高以上に匹敵する粘土層のうえに立脚していることになる。
篠原希氏は1972年の大阪生まれだが、信楽町黄瀬で作陶し、伊賀焼の聖地・丸柱に築いた窖窯で焼く。2007年には信楽焼の伝統工芸士に認定され、言わば古琵琶湖層の上を広く制作の場にしている若き陶芸家である。
窯変に憧れる
小さいころから大工の仕事が好きで、一日中見ていることもあった篠原氏は、将来はクラフト関係の仕事に就きたいと考えていた。そこで19歳のとき、職人を募集していた信楽の古谷製陶所に入所し、同製陶所を興した古谷信男氏に師事した。
1950年生まれの古谷信男氏は、粉引の制作と販売を大規模に展開する「窯屋」の二代目。原土からつくった陶土による柔らかな風合いと、古谷氏が好む真っ白な化粧土が人気の窯元だ。篠原氏はそこで8年間学び、小さな電気窯を買って独立し、黄瀬で制作を開始した。しかし粉引や刷毛目、それに信楽の窯業技術試験場で学んだ貫入ものなどを焼いたが、どれも師匠を越えることはできなかった。
粉引を制作したり、「生屋」として食いつないでいたりした合間に篠原氏が仕事仲間とトライしたのが、レンタルした登窯や窖窯の焼成。そこで焼き上がったピンク色の窯変を見て、自分で焼締の窯を持って焼いていきたいという気持ちが、焼成するたびに強くなった。
レンタル窯を焼いているうちに、窯づくりまで理解できるようになった篠原氏は、窯場の確保に奔走。友人の紹介で、2004年伊賀・丸柱の山際に土地を確保し、窖窯を築いた。
そこはかつて古谷道生(1946-2000)が、伊賀を焼くために窯を築いたことがある場所だった。食えない若い陶芸家が希望したら譲ってもいい、という遺言を残して確保していた窯場だった。好きな焼締作家が多い伊豆に行こうかと考えていたときで、篠原氏はその幸運をありがたく受け入れた。
古谷道夫が残した窯床をそのまま利用した窖窯は、棚板1枚が敷ける大きさで、焼成時間は約5日間。あぶりは灯油、攻め焚きは松の木で、窯詰めから一人で行う。温度計は使わず、熔けた自然灰が映し出す鉄棒の姿を見ながら焼成。頃合いを見計らって鉄棒で押して変形するのが篠原流だ。さらに裂け目を入れるときは、少しだけ口にキズを入れて成形し、その後は成り行きに任せで焼成しているが、それが伊賀焼の水指「破袋(やぶれぶくろ)」を思わせる焼き上がりになっている。信楽焼とか伊賀焼とかにこだわらず、太古からの素材の良さをそのまま引き出すための篠原氏独自の焼成手段としてなっているだ。
PROFILE
1972年 大阪生まれ
1991年 信楽の古谷製陶所に入り、古谷信男氏に師事
1998年 信楽窯業技術試験場釉薬科修了
1999年 信楽町黄瀬で独立
2000年 初個展(信楽・ギャラリー陶園)
2004年 伊賀に新たに窖窯を築く
2007年 信楽焼伝統工芸士に認定される
2012年 秀明文化基金賞