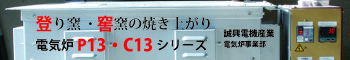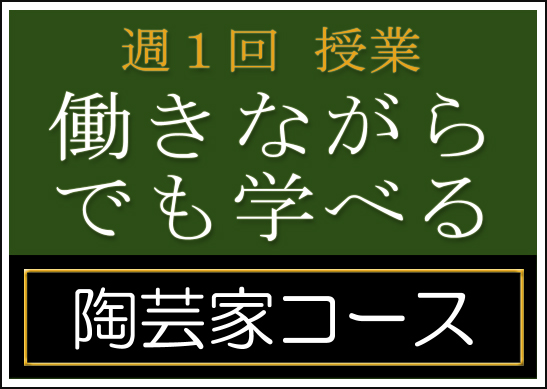若尾経
灰白釉と青磁釉に従う
高田徳利の里に生まれ、青磁に強い憧憬を持つ。試行錯誤の施釉を繰り返し、器物と釉薬を一体化させた作風を確立した。
その一つの、原初の志野を彷彿とさせる象牙瓷(ぞうげじ)は、美濃陶の新たな可能性をしめしている。
青磁に憧れる
黒い器体と、それをおおう象牙を思わせる黄味を帯びた灰白釉で陶芸界に衝撃を与えた若尾経氏は、高田徳利の生産地として知られる多治見市小名田町に生まれた。小名田や隣接する高田町では古くから、夢窓疎石が鎌倉時代に開いた虎渓山永保寺に納める焼き物を焼き、一八世紀後半からは高田徳利を大量生産した。焼き締まりのいい炻器質の土に恵まれていたためで、土灰釉が掛けられた高田徳利はほとんど水が漏れず、湯たんぽとしても重宝された。
曲りくねった旧道沿いに窯元が点在する小名田には、窯業に携わる人が圧倒的に多い。若尾氏のお祖父さんも例外ではなく、轆轤を挽いたり、大きな窯元の工場長も勤めたりした。そんなときぶらりと訪ねてきたのが、中国宋代の定窯の窯跡を発見し、中世日本の六古窯を再評価した陶磁研究家の小山冨士夫。小山は、「永仁の壺」事件で職を辞して六四年に作陶を開始し、陶芸家を目指していたのだ。七二年に五斗蒔に窯を築き、小名田でお祖父さんの轆轤を借りて挽いていたのだ。
折しも、荒川豊蔵が再興を果たした美濃陶が注目を集めていたときで、二〇〇三年に志野で岐阜県重要無形文化財保持者に認定された経氏の父利貞氏も、早くから作家活動に身を投じていた。そんな環境に育った若尾氏は、大学では写真を学んだが、やはり一人でも創作が可能な焼き物を選択した。
若尾氏は現在、陶器と磁器の両方を手掛けているが、陶器の場合は父親の工房を間借りする形をとっている。そこで制作しているのは、台湾の故宮博物館で見て改めて憧憬を強くした青磁と、氏が開発した灰白釉を掛けた象牙瓷。青磁では、岡部嶺男が世に送り出した米色青瓷も手掛けている。近くに住む陶芸の原材料会社に勤めていた方にもらった一五種類ほどの長石に、灰を加えて焼いたところ、見事な二重貫入の青磁ができ上がったのがきっかけだった。それまで少しは青磁を焼いたことがあったが、以後青磁に本格的に取り組み始めたのだった。しかし 二回目からは気泡が出たり、釉薬が裂けたりと、完璧な青磁は一つも焼き上がらなくなっていた。
釉薬に従う
大きな壁にぶち当たった若尾氏は、キズがでた場所や器物の形を詳細に検討し、キズが出そうなところには釉薬を掛けない方針に切り換えた。さらに、施釉面積が広くなるとキズのリスクが格段に高まることに気づき、大きな作品の場合は施釉面を小さく区切る方策を採った。試行錯誤を繰り返し、釉薬の性質に忠実に従ったことによって生まれたのが、稜線で施釉面を区切った青磁や、素地を模様の一部として露出させることもある一連の「象牙瓷」。ことに象牙瓷の茶碗の場合は、釉掛けのときの指痕を景色の一部として大胆に取り込み、斬新なデザインに仕上げることに成功している。
こうした、器物の形状と釉薬の一体化に取り組んだ作品は、コレクターの間だけでなく公募展でも高く評価されているが、美濃陶と無関係ではない。とくに、青磁釉の透明感を抑えることによって生まれた象牙瓷の灰白釉は、志野の原料として不可欠な長石と灰釉とのバランス関係を綿密に計算した結果生まれたもので、日本で初めて長石の志野釉を掛けたと言われる「白天目茶碗」とほぼ同じテイストを持つ。原初の志野を彷彿とさせる象牙瓷には、美濃陶の新たな可能性が秘められている。
WAKAO KEI PROFILE
1967年 岐阜県多治見市に生まれる
1993年 日本大学芸術学部写真学科卒業
1995年 多治見氏陶磁器意匠研究所修了
1997年 日本陶芸展入選
1997年 朝日陶芸展秀作賞
1997年 出石磁器トリエンナーレ入選
1998年 国際陶磁器フェスティバル美濃銅賞
1998年 金沢わん・One大賞招待出品
1999年 信楽陶芸の森陶芸の20世紀展招待
2005年 若尾利貞・経親子作陶展(近鉄四日市店)
2010年 第5回パラミタ陶芸大賞展大賞
松坂屋本店、日本橋三越本店などで個展開催