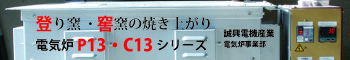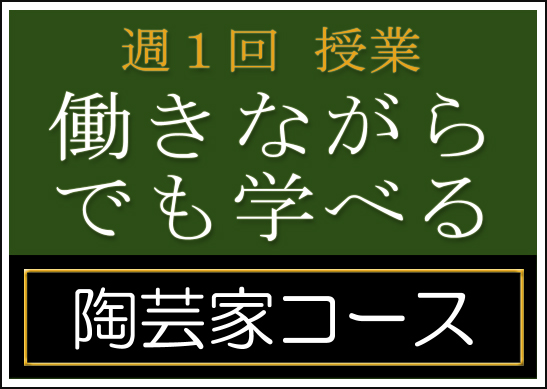市野信水
丹波伝統の茶陶づくり
丹波焼を代表する茶陶作家の一人で、信水窯の二代目。丹波の数種類の原土で、板起しという成形法を維持しながら、江戸時代に始まる丹波茶陶の伝統を、色濃く受け継ぐ。
三本峠で始まる丹波焼
丹波焼の窯が最初に築かれたのは、三田市と接する三本峠。近隣で焼かれていた須恵器の影響を受けた村民によって、平安時代末期に産声をあげた。鎌倉時代になると壺、甕、すり鉢を焼き、江戸時代には三本峠の北西に位置する釜屋に朝鮮式の半地下式の登り窯を築いて大量生産を開始。村の約8割に当たる110軒ほどが焼き物に従事するという大窯業地に発展した。
明治時代には窯元が130軒ほどに達し、現在は60軒ほどに半減してしまったが、昭和の初期に訪れた民藝運動の柳宗悦が、「もっとも日本らしい」と賞賛した日本の日常生活に根ざした焼き物づくりは、いまも受け継がれている。
最初に登り窯が築かれた釜屋には現在窯元は一軒もなく、現在は兵庫陶芸美術館がある下立杭とその北の上立杭に窯元が集中している。下立杭はもともと丹波焼の中心であったが、山が間近に迫り、利用できる土地は限られている。それに比して上立杭は比較的平地が多く、窯場だけ移した窯元や新たに独立した陶芸家が多い。
江戸時代からの茶陶を受け継ぐ
茶陶を専門とする市野信水氏の信水窯は、陶芸家・市野丹泉の次男で初代の信水が、1968年に窖窯と登り窯を現在地に築いたことから始まる。1932年生まれの初代は一時日展に出品していたが、茶陶を得意とした丹泉の血筋を受け継いで個人作家として独立。当初から茶陶に専念し、1983年には日本工芸会正会員となり、丹波焼を代表する茶陶作家の一人となった。
壺、甕を始めとする生活雑器の生産からスタートした丹波焼は、民藝運動家の評価も重なり、そのイメージが強い。しかし、茶陶づくりも盛んで、その始まりは江戸時代前期に遡ることができる。小堀遠州らの指導により、「遠州丹波」と称された茶碗、水指、茶入などの名器が次々と誕生し、とくに高く評価された茶入が、小堀遠州の茶会で使用されたことが記録に残っている。
こうした江戸時代からの茶陶づくりの伝統は、信水窯を始めとする立杭の窯元で代々脈々と受け継がれている。というのは、立杭は土地が限られているため新たに人が入り込むが余地がほとんどなく、江戸時代の頃からの家筋が現代まで存続しているからだ。現在の窯元が十数代にわたって丹波焼に携わってきたことになるが、菩提寺の過去帳が焼失したため、それを明らかにすることはできない。
受け継がれる丹波茶陶
京都で学んだ初代の長男・克明氏が、立杭に戻ったのは23歳のとき。陶芸ブームがやや下火になってはいたが、初代のもとで修行することを選んだ。そして、64歳で亡くなった初代の名跡を5年後の2002年に継ぎ、現在二代目信水として、茶陶づくりに専念している。
丹波焼で伝統的に使われてきた土は、山土と田土だ。歴史が古いのが山土で、現在は三田市四ツ辻から採取されている。登り窯時代から使われるようになった田土は現在、篠山の弁天産を使うようになっているが、ともに組合の坏土工場が1963年に精製を始めるまでは、各窯元がふるいに掛けたり水ひを行ったりしていた。信水窯は、その昔ながらのやり方を踏襲している。
先代から集め始めた特徴のある山土や田土の原土が6種類ほどあり、それを単身で使用したり、混ぜ合わせたりして、茶陶づくりに生かしているのだ。
茶入、茶碗、水指などの信水窯の茶陶は、小さなものから大きなものまで、立杭独特の左回転の轆轤で成形される。それもほとんどが板起しで、底に付いたもみ殻の痕が、焼締陶ならではの奥深さを醸し出す。茶陶の焼成に使われることが多いのが半地下式の窖窯で、1,200度を30時間から40時間維持しながら焼く。熔けずに器の表面に顔を出した細かな石粒が、自然釉、ほのかな緋色や焦げなどと、控えめながら絶妙なハーモニーを奏でているのが、信水窯の茶陶だ。
ICHINO SHINSUI PROFILE
1957年 丹波立杭焼に初代・市野信水の長男として生まれる
1977年 京都造形芸術学院卒業(現在、京都造形芸術大学)
1980年 丹波で初代の許で指導を受ける
1986年 日本工芸会近畿支部入選(以後毎年)
1989年 田部美術館茶の湯の造形展入選(以後11回)
1990年 日本伝統工芸展初入選(以後5回)
1993年 県工芸美術展神戸新聞社大賞
1993年 蓬菜会展(清水卯一主宰)に出品(以後毎年)
1993年 日本工芸会正会員に推挙
2001年 日本陶芸展入選
2002年 大阪高島屋で二代市野信水襲名記念展を開催
大阪高島屋、米子高島屋、神戸大丸、ぎゃらりい栗本などで個展多数開催
日本工芸会正会員