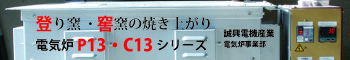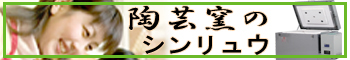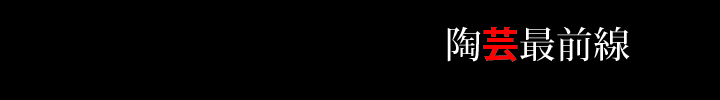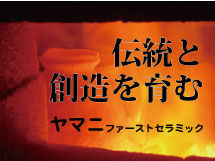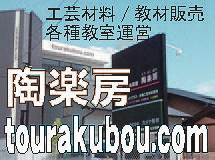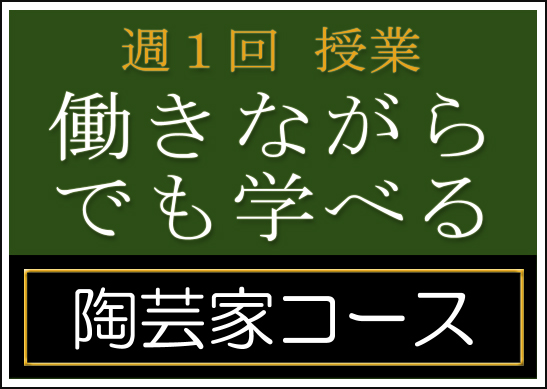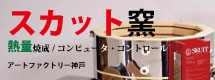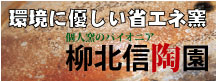杉浦康益 陶の博物誌展—新たな息吹を求めて—
2022年6月4日(土)〜10日(金)
柿傳ギャラリー
新宿区新宿3-37-11 安与ビルB2F
03-3352-5118
1949年東京に生まれ、75年東京藝術大学大学院美術研究科陶芸専攻修了。在学中に「やきものは石である」という教えに、河原の石のように成形した『陶の石』シリーズを手掛け、オブジェ陶の制作を開始した。次に、陶製の柱やブロックを無数に積み上げた『陶の木立』シリーズに取り組むとともに、84年神奈川・真鶴に築窯。2000年から貝や植物をモチーフにした『陶の博物誌』シリーズの制作を開始し、それに移り住んだ真鶴の山の花がモチーフとして加わった。
06年パラミタ大賞展大賞、2012年度日本陶磁協会賞をそれぞれ受賞しているが、自然の花などをテーマに生命の圧倒的なエネルギーを力強く表現する独自のコンセプトは、イタリア、台湾、中国など海外でも高い評価を受けている。
3年ぶりとなる今展には、「野イチゴの花」「ヒマワリの種子」「山法師」「山桃」「芍薬」「柘榴」ほかが出品予定。