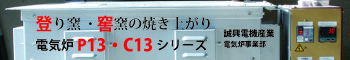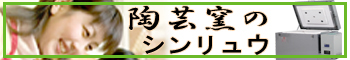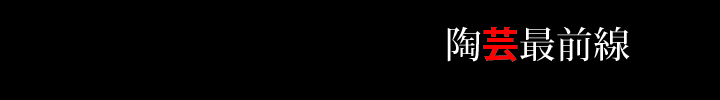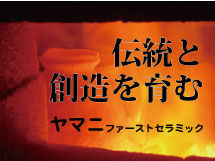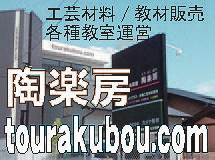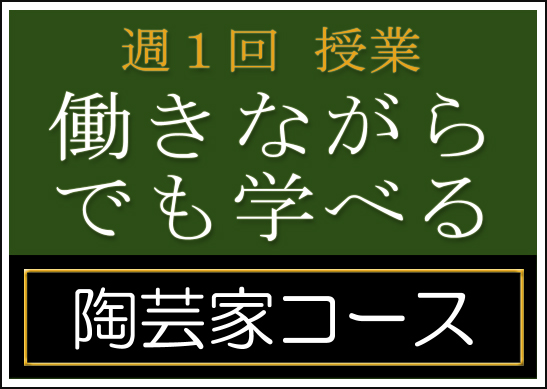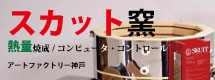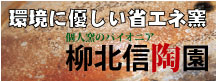珠洲焼 中世・日本海に華ひらいたやきものの美
2019年10月5日(土)〜11月10日(日)珠洲焼資料館
石川県珠洲市蛸島町1−2−563
0768-82-6200
|
|
|
|
能登半島の先端部に築かれた窯で焼かれたのは、甕、壺、摺鉢などの日用品で、海に突き出た地の利を生かし、東北、北陸の日本海沿岸各地や遠くは北海道まで流通した。14世紀には最盛期を迎え、日本列島の4分の1を商圏としたが、15世紀後半には急速に衰えて廃絶した。
長らく「幻の古陶」と呼ばれていた珠洲焼は、1979年約500年ぶりに復興され、89年には石川県の伝統工芸品の指定を受け、現在46人の陶芸家が制作に励む。本展は、珠洲焼の復興40周年と珠洲焼資料館開館30周年を記念するプロジェクトで、珠洲焼の代表作70点が集結する。期間中は珠洲市内で、シンポジウムやアートツアーほかが企画されている。