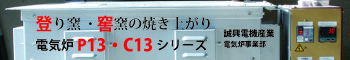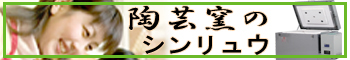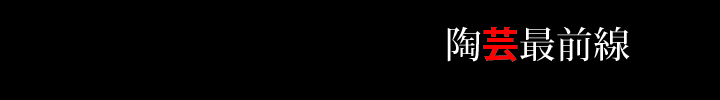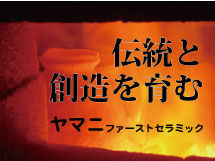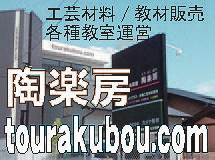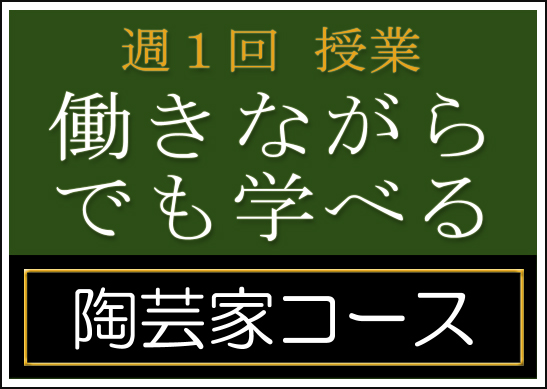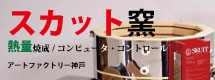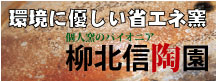人間国宝 鈴木藏展
2025年9月24日(水)〜9月29日(月)
髙島屋日本橋店美術画廊
中央区日本橋2-4-1
03-3211-4111
2025年10月15日(水)〜20日(月)
髙島屋大阪店6階美術画廊
大阪市中央区難波5-1-5
06-6631-6382
2025年10月29日(水)〜11月3日(月)
髙島屋京都店6階美術画廊
京都市下京区四条通河原町西入真町52番地
075-221-8811
|
|
|
1934年岐阜県土岐市に生まれ、窯業技術者であり、釉薬の研究者でもある父の助手として働いたのち、本格的に作家の道に進む。志野は薪窯で焼くのが最良とされていた中、1960年後半にガス窯による焼成に成功し、独自の作陶スタイルを確立した。以降、日本陶磁協会賞をはじめとする数々の公募展で受賞を重ね、1994年には「志野」において重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定され、さらに2024年には文化功労者としても顕彰された。
桃山陶芸の原点を踏まえなが、土、釉薬、造形を様々に組み合わせて独自の表現を追求し、日本人特有の美意識や感性、そして自然への深い敬意が創作の根幹にあり、その精神性はすべての作品に映し出されている。
本展では独自の創意と重厚感にあふれた茶碗を中心に、花器や書などの作品群を一堂に展観する。